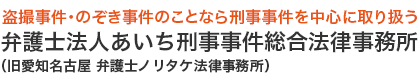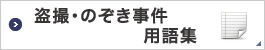盗撮事件・のぞき事件と執行猶予
※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。
このページの目次
1 執行猶予とは
執行猶予とは、罪の重大さや前科の有無、反省状況等の事情を考慮して、裁判所の言い渡す有罪判決において刑の執行を一定期間猶予する制度です。
通常、執行猶予がない実刑判決が言い渡されると、裁判が確定したらすぐに刑務所へ入る、あるいは罰金の納付が強制されることとなります。
たとえば、2年の拘禁刑の実刑判決が言い渡された場合には、裁判が確定したらすぐに刑務所へ入ることとなります。
これに対し、執行猶予付判決が言い渡されると、その判決で定められた期間(裁判が確定した日より1年~5年間)の刑の執行が猶予され、すぐに刑務所に入らなくてもよい、あるいは罰金の納付が猶予されることとなります。
たとえば、「拘禁刑1年、執行猶予3年」という判決が言い渡された場合には、裁判が確定してから3年の間、拘禁刑の執行が猶予され、その間は刑務所へ入ることを猶予されることとなります。
執行猶予付判決が下されると、今まで通りの日常生活を送りながら更正を図ることができます。そして、執行猶予期間を無事に経過した場合、刑の言い渡しの効力は失います(刑法27条)。
そのため、執行猶予付判決で言い渡された拘禁刑等の効力が失う結果、刑務所へ行く必要はなくなります。
2 執行猶予を得ることのメリット
- 執行猶予期間中は刑務所へ入らなくて済む
- 会社や学校に行くこともでき、日常生活を送りながら更正を図ることができる
3 再度の執行猶予
執行猶予期間中の犯罪については、一般的に実刑判決になると言われています。
しかし、例外的に再度執行猶予が付される場合があります。
法律上、
①2年以下の拘禁刑の言い渡しを受け
②情状に特に酌量すべきものがある
③再度の執行猶予期間中における犯行ではない(保護観察の仮解除中を除く)
という3点を満たす場合、執行猶予中に犯した罪について再度執行猶予判決を得ることが可能となります。
執行猶予制度の改正
改正刑法に基づき、2025年6月1日から、新しい執行猶予制度が施行されています。2025年6月1日以降の事件に適用される新しい執行猶予制度の主な改正点は以下になります。
(1)再度の執行猶予の条件緩和
これまでは、1年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合のみ、再度の執行猶予が可能でした。
改正後は、2年以下の拘禁刑(懲役と禁錮の一本化)を言い渡す場合にも、再度の執行猶予が可能になります。
拘禁刑の上限が1年から2年に引き上げられたため、再度の執行猶予の対象となる刑の幅が広がります。
(2)保護観察付執行猶予中の場合の再度の執行猶予
改正前は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合、再度の執行猶予は不可能でした。
改正後は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合でも、再度の執行猶予が可能となります。
ただし、再度の執行猶予期間中に再犯した場合は、保護観察の仮解除中を除き、さらに再度の執行猶予を付すことはできません。
(3)執行猶予期間満了後の再犯の場合の効力継続
執行猶予期間中の再犯について公訴が提起された場合、執行猶予期間満了後も一定の期間は、刑の言渡しの効力及びその刑に対する執行猶予の言渡しが継続しているものとみなされます。
これにより、いわゆる「弁当切り」(前刑を失効させるために公判の引き延ばしをする行為)はできなくなったと考えられます。
自分の罪について、執行猶予がつくのかわからない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
早期に相談することで、適切な弁護方針を立て、起訴される前に事件を解決できる場合もありえます。
執行猶予にしてほしい場合には、刑事事件について経験豊富な弁護士に相談し、具体的な事情のもと執行猶予の獲得へ向けた弁護活動を行っていくことが重要です。
盗撮事件・のぞき事件で執行猶予にしたいときには、刑事事件について経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談下さい。